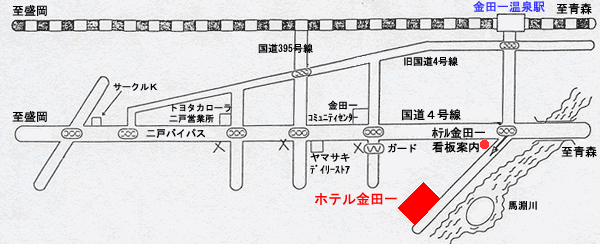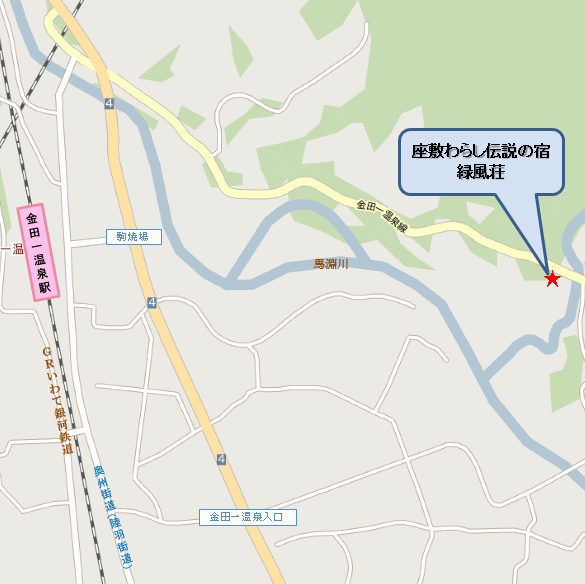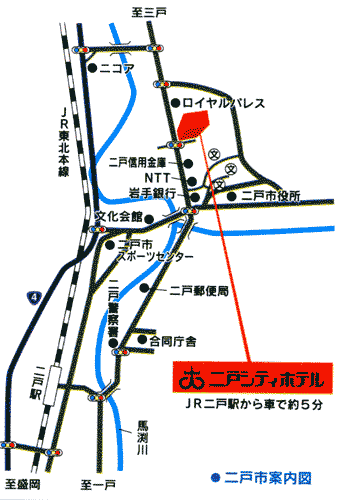戦国時代の最後の戦火ともいわれる「九戸政実の乱」の舞台となった九戸城(くのへじょう)は、岩手県二戸市にある国指定史跡です。現在は整備された公園として開放され、自然地形を活かした美しい土塁や堀が当時のまま残されており、歴史ファンを中心に多くの観光客が訪れています。
特に注目されているのは、九戸政実がわずかな兵で豊臣秀吉の大軍と戦ったという壮絶な背景。彼の武勇と誇りが刻まれたこの地を訪れることで、教科書では味わえない“生きた歴史”を体感できます。
そんな九戸城の観光において大切なのが、宿泊場所の選定です。交通の便が限られているため、事前にしっかりとした宿選びをすることが旅の満足度を大きく左右します。
この記事では、九戸城観光を快適に楽しむためにおすすめの宿泊施設を5件厳選。。また、九戸城の歴史・見どころ・モデルコース・周辺観光なども徹底解説し、初めての訪問でも安心して旅を楽しめる内容に仕上げています。
歴史の風を感じながら、温泉や美食で癒される――そんな旅をあなたも体験してみませんか?
九戸城観光に便利なおすすめ宿泊施設5選
岩手の名湯 侍の湯 おぼない
「侍の湯 おぼない」は、金田一温泉郷の静かな場所に佇む、源泉かけ流しの温泉宿です。風情ある昭和初期の木造建築を活かした本館は、どこか懐かしい雰囲気を持ち、館内の随所に時代を感じさせる意匠が施されています。温泉は「玉の湯」として知られ、肌触りの柔らかいアルカリ性単純温泉。湯上がり後の肌がしっとりすると評判です。
お料理は地元岩手の旬の食材を使った会席料理が提供され、川魚や山菜、地元米のご飯など、田舎の贅沢を味わえます。
アクセス情報:
-
金田一温泉駅から車で約7分
-
九戸城までは車で約20分(約12km)
周辺観光スポット:
-
金田一温泉郷 散策(徒歩圏内)
-
馬仙峡 展望台(車で約15分)
-
浄法寺漆芸の里(車で約25分)
落ち着いた環境でゆっくりと歴史を感じたい方にぴったりの宿です。
仙養舘(せんようかん)
「仙養舘」は、家庭的なおもてなしと昭和情緒が溢れる温泉宿。豪華な設備ではなく、どこかホッとするような安心感のある宿で、リピーターも多いのが特徴です。源泉かけ流しの天然温泉は、内湯と露天風呂があり、金田一温泉特有の優しい泉質が旅の疲れを癒してくれます。
お料理は地元の山菜や川魚を使用した郷土料理。朝食も手作りで、旅のエネルギー補給に最適です。
アクセス情報:
-
金田一温泉駅から車で5分
-
二戸駅から車で約15分
-
九戸城跡まで車で約20分(約11km)
周辺観光スポット:
-
金田一温泉足湯(徒歩3分)
-
岩手県立二戸病院(車で10分)
-
九戸資料館(車で15分)
観光の拠点としてはもちろん、家庭的なぬくもりを感じたい方におすすめです。
ホテル金田一
駅からのアクセスが良好で、ビジネスや観光の拠点として人気の「ホテル金田一」。館内は清潔感があり、和室・洋室どちらも用意されています。大浴場も完備されており、旅の疲れをしっかり癒せます。
無料駐車場が広く、車での旅行にも最適。リーズナブルな料金設定も魅力です。
アクセス情報:
-
金田一温泉駅から徒歩15分・車で3分
-
二戸駅から車で約15分
-
九戸城跡まで車で約20分(約12km)
周辺観光スポット:
-
金田一温泉神社(徒歩10分)
-
金田一温泉センター(徒歩5分)
-
馬仙峡(車で15分)
手頃な価格で快適な宿泊をしたい方には最適な選択肢です。
座敷わらし伝説の宿 緑風荘
「座敷わらし伝説の宿 緑風荘」は、その名の通り座敷わらしが出ると噂される伝説の宿。多くの著名人や芸能人も訪れており、「運が開ける宿」として全国的にも有名です。2019年に再建された館内は新しく、伝統と快適さを兼ね備えた和モダンな空間となっています。
温泉は源泉かけ流しで、美肌の湯として女性にも人気。特別室や記念撮影スポットなど、非日常を味わえる仕掛けが豊富です。
アクセス情報:
-
金田一温泉駅から車で約4分
-
九戸城まで車で約20分(約13km)
周辺観光スポット:
-
金田一温泉文化センター(車で5分)
-
二戸シネマ(車で10分)
-
南部美人 酒蔵見学(車で15分)
パワースポット好き、神秘的な体験を求める方にはうってつけの宿です。
天然温泉 黎明の湯 二戸シティホテル
「二戸シティホテル」は、二戸市の中心部に位置するビジネスタイプのホテルですが、天然温泉「黎明の湯」を備えているのが最大の魅力。観光・ビジネス問わず利用者が多く、シングルルームも広々としており快適です。
館内にはレストランや会議室もあり、朝食付きプランも充実。夜には温泉にゆっくり浸かり、疲れた体をリフレッシュできます。
アクセス情報:
-
JR二戸駅から徒歩約15分・車で5分
-
九戸城まで車で約5〜10分(約2km)
周辺観光スポット:
-
二戸駅前商店街(徒歩10分)
-
九戸資料館(徒歩15分)
-
浄法寺漆芸の里(車で20分)
「駅近+温泉付き」を両立したい方にはぴったりの宿です。
歴史
九戸城の築城と九戸政実
九戸城(くのへじょう)は、岩手県二戸市に位置する戦国時代の山城で、南部氏の一族である九戸氏が築いたとされます。築城時期には諸説ありますが、16世紀中頃、九戸政実(くのへまさざね)の時代に本格的な城郭として整備されたと見られています。
九戸政実は、南部氏の中でも特に実力を持ち、領内の民からも慕われた名将でした。当時、南部家では家督争いが激化しており、政実はその内紛に巻き込まれました。結果として、政実は一族の本家筋である南部信直との対立関係に陥り、これが後に「九戸の乱」へとつながっていきます。
城は馬淵川と白鳥川という2つの川に挟まれた天然の要害に築かれており、自然の地形を巧みに利用した堅固な構造をしていました。堀切や土塁、曲輪(くるわ)といった防御施設も整っており、当時の築城技術の高さがうかがえます。
現在の九戸城跡は国の史跡として整備されており、本丸跡や土塁の跡が美しく保たれています。これらの遺構からは、九戸政実がいかに戦略的思考に優れていたかが感じられます。築城そのものが、政実の軍事的才能を如実に表す証でもあり、訪れる人々は自然とその時代背景に思いを馳せることができるでしょう。
九戸城を訪れる際には、政実がどのような想いでこの城を築いたのかを想像して歩くと、より一層その魅力を感じられます。見た目だけではなく、歴史の文脈を知ることで、この城の重厚な価値が伝わってくるのです。
九戸政実の乱とは?
「九戸政実の乱」は、1591年に起きた東北地方最大級の戦乱の一つで、戦国時代の終焉を象徴する出来事ともいわれています。発端は、南部家中での家督争い。九戸政実は南部家の一族でしたが、本家筋である南部信直が豊臣秀吉により南部家当主として認められたことで、政実は反発します。
政実は自らの正統性を主張し、約5000の兵を集めて立ち上がりました。この動きを重く見た豊臣秀吉は、奥州仕置の名のもとに全国から諸大名を動員。蒲生氏郷や浅野長政らを中心とした総勢6万ともいわれる大軍が九戸城を包囲しました。
戦力差は歴然としており、城はわずか数週間で陥落します。政実は降伏を申し出ますが、約束は反故にされ、捕らえられた上で斬首されました。この事件は「だまし討ち」として後世に語り継がれ、政実の忠誠心や信念、そしてその非業の最期が今も多くの人の心を打ちます。
この戦いは、戦国時代の終焉を告げる最後の合戦ともいわれ、九戸城跡を訪れる人々にとっては、ただの城跡ではなく「時代の節目を刻んだ地」として強い印象を残します。
現在も地元では九戸政実を英雄として顕彰する動きがあり、九戸政実を題材としたイベントや資料展示なども行われています。歴史ファンにとっては必見の地であり、そのスケールと物語性の豊かさは訪れる価値を十分に感じさせてくれるでしょう。
九戸城が国指定史跡となった理由
九戸城は1979年(昭和54年)に国の史跡に指定されました。指定の理由としては、東北地方の戦国時代末期の山城として、築城技術や防御構造が非常に優れており、かつ保存状態が良好だったためです。
特に注目されたのは、自然地形を活かした「堀切(ほりきり)」や「馬出(うまだし)」と呼ばれる防御施設の遺構が明確に残っていたこと。これは、戦国末期の戦略的な城づくりを知る上で非常に貴重な資料となるものでした。
また、九戸政実という歴史的人物が実際に籠城戦を行ったことで、政治的・軍事的にも重要な役割を果たした城としての評価が高まったのです。現在も発掘調査や整備作業が継続的に行われており、学術的価値は非常に高いといえます。
さらに、九戸城の周辺地域が「九戸政実の乱」という歴史的事件の舞台であったことも大きな理由の一つです。この史跡は、単なる構造物の遺跡というだけでなく、「歴史の転換点となった地」として、文化財的な意味でも非常に重みがあります。
訪れる人にとっては、歴史を肌で感じられる「生きた教科書」のような存在。子どもから大人まで、誰でも楽しみながら学べる場所として、近年では教育旅行の行き先としても注目を集めています。
九戸政実の人物像と地元での評価
九戸政実(くのへまさざね)は、戦国時代末期の武将で、南部氏の分家筋にあたる九戸家の当主でした。九戸城を本拠に、北東北の統治に力を尽くし、当時の領民からは「公正な支配者」「義に厚い人物」として非常に慕われていました。
南部家の家中争いでは、豊臣政権に仕える南部信直と対立し、結果として「九戸の乱」を起こすに至ります。政実は反乱者という位置づけで討伐されますが、その行動の背景には、家臣や領民を守ろうとする強い責任感と、信直の政権下での不公平な支配への反発があったと考えられています。
現在でも、九戸政実は地元・二戸市や九戸村の人々にとって、単なる反乱者ではなく、「地元の英雄」として語り継がれています。毎年9月には「九戸政実まつり」が開催され、子どもたちが武者行列に参加するなど、地域の誇りとして根付いているのです。
このように、政実の評価は単に史実だけでなく、地元文化・郷土愛とも結びついています。観光客が九戸城を訪れる際、政実の人柄や地元の人々との関係性を理解すると、より深い感動が得られるでしょう。
九戸城の廃城とその後の変遷
九戸城は、1591年の「九戸政実の乱」後、落城とともに機能を失い、豊臣政権の意向によって廃城となりました。九戸政実の処刑後、城の再利用はなされず、そのまま放置され、次第に自然に帰っていくこととなります。
しかし、江戸時代以降も地元では「政実公の城跡」として語り継がれ、城跡の存在は地域の重要な歴史遺産として認識されていました。特に明治時代以降、郷土史研究が進む中で、九戸城の歴史的価値が再評価されるようになります。
昭和30年代から地元自治体や郷土史家の働きかけによって保存活動が本格化し、1979年には晴れて「国指定史跡」として登録。その後、整備事業が段階的に進み、現在では遊歩道や解説板、史跡公園としての整備がなされ、多くの観光客が訪れるようになっています。
こうした経緯から、九戸城は単なる遺跡ではなく、「地域とともに歩んできた文化財」と言える存在です。廃城から400年以上経った今も、その姿を今に伝えている九戸城は、まさに時を越えて語り継がれる「生きた遺産」です。
見どころ
本丸跡と堀切の構造美
九戸城の中でも圧巻の見どころは、本丸跡に残る堀切(ほりきり)の構造です。堀切とは、敵の侵入を防ぐために山の尾根を断ち切るように掘られた堀のことで、九戸城ではその形状が今もはっきりと確認できます。
本丸跡は高台に位置し、周囲を急峻な地形と複数の堀切で守られていました。これにより、攻め込もうとする敵兵は迂回を強いられ、防御側は上から弓や槍で迎撃するという戦術が可能でした。
現在も遊歩道が整備されており、本丸跡からは城下の地形や二戸市街地を一望できます。季節ごとに表情を変える自然とともに、かつての戦場の風景を想像しながら歩くと、まるで時代を遡ったような気分になります。
現地には解説看板もあり、初心者でも分かりやすく歴史の背景を学べるようになっています。特に堀切の深さと鋭角な造形美は、当時の戦術や築城技術の高さを感じさせてくれます。
史跡好き・歴史マニアはもちろん、家族連れや学生にもおすすめのスポットです。
二の丸・三の丸跡の広がりと防御線
九戸城は本丸だけでなく、二の丸・三の丸といった複数の郭(くるわ)が配置された広大な構造を持っていました。これらの副郭は、主に家臣団の居住区や兵の配置拠点として使用され、防御の要でもありました。
二の丸跡は本丸に隣接しており、地形的にも本丸を支える形で築かれています。敵が本丸に到達する前に必ず通らなければならないルート上にあるため、防衛力を高める役割を果たしていました。
三の丸はさらに外側に位置し、物資の保管や馬の繋ぎ場、さらには緊急時の避難場所としても機能していたとされています。
現在の二の丸・三の丸跡は整備され、芝生が広がる散策路として解放されていますが、地形の高低差や土塁の跡などから、当時の城郭構造を想像することができます。
訪れる際は、本丸跡との位置関係を意識しながら歩くと、より臨場感が増します。九戸城の構造的魅力を知るうえで、二の丸・三の丸の存在は見逃せないポイントです。
九戸城の土塁と石垣跡
九戸城のもうひとつの大きな見どころは、「土塁(どるい)」と「石垣跡」です。九戸城は、自然の地形を活かした山城であるため、現代の城郭に見られるような高い石垣や天守閣はありませんが、むしろその素朴で力強い構造が、戦国時代のリアルな姿を伝えてくれます。
特に土塁は、全長数百メートルにもおよび、一部では高さが2〜3メートル残っている箇所もあります。これは、当時の築城技術と労働力の集約によるもので、天然の防御施設として非常に有効でした。
また、九戸城では近年の発掘調査によって、一部に石積み構造が施されていたことが判明しています。これまで「純粋な土の城」とされていた九戸城に、石垣的要素があるというのは大きな発見でした。現地ではその石積み跡の保存区画が設けられており、見学が可能です。
これにより、九戸城が単なる地方の山城ではなく、当時の最先端技術を取り入れた「ハイブリッド構造の城」であったことがわかります。
土塁と石垣のコントラスト、そしてそこから見える防御戦略は、まさに戦国の知恵の結晶。見上げれば木々の間から差し込む光とともに、当時の侍たちの息遣いすら感じられるかもしれません。
現地の案内施設と解説板
初めて九戸城を訪れる方でも安心なのが、整備された現地の案内施設や解説板の存在です。九戸城跡は現在「九戸城跡史跡公園」として整備されており、散策路、案内看板、ベンチ、トイレ、駐車場などが完備されています。
入り口には観光案内所が設置されており、そこで地図やパンフレットを入手することができます。特にパンフレットには、曲輪の配置や堀・土塁の形状がイラスト付きで解説されており、城巡りが初めての人にもわかりやすい構成です。
また、敷地内には複数の案内板が設置されており、それぞれのエリアごとに「どんな役割を持っていたのか」「当時どのような建物があったのか」などが丁寧に解説されています。QRコードが付いていて、スマホで読み取ると音声ガイドや追加情報も確認できる箇所もあります。
観光案内所のスタッフも非常に親切で、事前に見どころの優先順位や滞在時間に応じた散策ルートを教えてくれることもあります。時間に余裕があれば、ぜひ立ち寄って情報を整理してから見学を始めると、より充実した時間を過ごせます。
歴史の深さと現代的な観光サポートが融合した九戸城は、まさに“歩いて学べるフィールドミュージアム”です。
四季折々の景観とベストシーズン
九戸城は、歴史的価値だけでなく、四季折々の自然が楽しめる景観スポットとしても人気です。春には桜、夏には深緑、秋には紅葉、そして冬には雪景色と、訪れる季節ごとにまったく異なる表情を見せてくれます。
**春(4月中旬〜下旬)**には、城跡の周辺に植えられたソメイヨシノが見事に咲き誇り、多くの地元民や観光客が花見に訪れます。特に本丸跡から二の丸方面に続く道は、まるで桜のトンネルのような景観に包まれます。
**夏(6月〜8月)**は、緑が濃く、木陰が心地よいハイキングコースになります。城跡全体が森の中にあるため、涼しく散策できるのも魅力の一つです。
**秋(10月中旬〜11月上旬)**には、紅葉が見頃を迎えます。特に堀の周囲にあるモミジやイチョウが色づき、金色と赤のコントラストが訪れる人の目を楽しませてくれます。カメラを片手に訪れる人も多く、写真スポットとしてもおすすめです。
**冬(12月〜2月)**は雪が積もり、まるで水墨画のような静寂な美しさに包まれます。ただし積雪が多い日には足元が悪くなるため、見学の際は滑りにくい靴や防寒対策が必要です。
観光のベストシーズンは「春」と「秋」とされていますが、それぞれの季節に魅力があるため、どの時期に訪れても新しい発見があるでしょう。
モデルコース
歴史探訪1日満喫コース(車利用)
九戸城観光を最大限楽しむためのおすすめモデルコースとして、まずご紹介したいのが「歴史探訪1日満喫コース」です。このコースは、マイカーまたはレンタカーを使って効率的に観光スポットを巡るプランで、移動時間が短く済むため、観光時間をたっぷり取ることができます。
【スケジュール例】
-
9:00 二戸市内の宿を出発
-
9:15 九戸城跡に到着・散策(約1時間)
-
10:30 九戸資料館見学(展示や映像資料で理解が深まる)
-
12:00 ランチ(地元のそば屋や定食店がおすすめ)
-
13:30 南部美人酒蔵見学(試飲あり)
-
15:00 馬仙峡展望台で絶景体験
-
16:30 宿に戻り、温泉でリラックス
このコースの最大の魅力は、「歴史」「文化」「自然」の3要素を1日で体験できる点です。九戸城の散策では、堀や土塁などの遺構を実際に歩くことで、教科書では得られないリアルな歴史の重みを感じられます。続く資料館では、九戸政実の人物像や戦乱の背景について、パネルやジオラマで詳しく学ぶことが可能です。
午後からは、南部地方の名酒「南部美人」の酒蔵見学へ。お酒に詳しくない方でも、ガイドの丁寧な説明と清酒の奥深さを体感できます。
最後は馬仙峡の展望台で、渓谷を望む絶景を楽しんで1日を締めくくります。滞在時間に余裕があれば、途中でカフェや直売所にも立ち寄ってみましょう。
徒歩と公共交通で楽しむ城下町散策コース
車を使わず、徒歩とバス・電車を活用して巡る「城下町ゆったり散策コース」は、歴史を肌で感じながらのんびりと過ごしたい方向けのプランです。移動時間に追われることなく、時間の流れを感じながら歩く旅の良さが詰まっています。
【スケジュール例】
-
9:30 二戸駅に到着
-
9:45 観光案内所でマップを入手
-
10:15 バスで九戸城跡へ(所要約15分)
-
10:30 九戸城跡散策(約1時間半)
-
12:00 バスで市街地へ戻る
-
12:30 地元食堂でランチ(郷土料理や手打ちそば)
-
14:00 二戸シティホテルで日帰り入浴またはカフェ休憩
-
15:30 九戸資料館や二戸駅前商店街散策
-
17:00 帰路へ
車がなくても快適に楽しめるこのコースは、観光施設の立地やアクセスが良好な二戸エリアならでは。特に九戸城跡周辺は、散策路や案内看板が整備されており、徒歩での見学にも最適です。
地元グルメや銘菓も充実しているので、お土産選びにも困りません。観光の合間に温泉施設や喫茶店で休憩をはさめるのも、このコースの嬉しいポイントです。
子どもと楽しむファミリー歴史体験コース
歴史スポットというと大人向けのイメージがありますが、九戸城は子どもでも楽しめる工夫が随所に凝らされています。そこでおすすめしたいのが、親子で歴史に触れながら遊べるファミリー向けモデルコースです。
【スケジュール例】
-
10:00 九戸城跡で自由散策&クイズラリー(事前にプリント持参)
-
11:30 芝生広場でお弁当ランチ(ピクニック気分)
-
13:00 九戸資料館でジオラマと映像資料を見学
-
14:30 緑風荘で「座敷わらし体験コーナー」見学
-
15:30 地元のお菓子屋でお土産探し
-
16:00 宿へチェックイン(夕食にお子様メニューあり)
このコースでは、九戸城の広い敷地や芝生を活用し、のびのびと遊びながら歴史に触れることができます。資料館では子ども向けの解説資料や映像もあり、飽きずに見学可能です。
緑風荘では、座敷わらし伝説にまつわる展示があり、子どもたちの好奇心をくすぐります。歴史と民話の両方を一度に学べる、貴重な教育体験の場となるでしょう。
温泉と自然を堪能する癒しのリトリートコース
旅の目的が「癒し」「リフレッシュ」であれば、九戸城を中心にしつつ、温泉と自然をゆっくり楽しむリトリートコースがおすすめです。静かな時間を大切にしたい大人の旅にぴったりです。
【スケジュール例】
-
10:00 九戸城跡を散策(早朝の静けさがおすすめ)
-
11:30 金田一温泉へ移動し、日帰り入浴
-
13:00 温泉宿で昼食(予約推奨)
-
15:00 馬仙峡や展望台で自然散策
-
17:00 宿にチェックイン、部屋でのんびり過ごす
温泉地である金田一エリアは、肌に優しい湯質で「美肌の湯」として知られています。散策後の入浴は、格別な癒しとなるでしょう。
馬仙峡や展望台では、深呼吸しながら自然を味わう時間が過ごせます。旅の疲れを癒すには最適な1日プランです。
フォトスポット巡りとインスタ映えコース
最後に紹介するのは、写真好きにおすすめの**「フォトジェニック九戸旅」コース**です。歴史や自然を背景に、素敵な写真を撮りながら旅の思い出を残したい方にぴったり。
【スケジュール例】
-
9:30 九戸城跡へ(早朝の柔らかな光で撮影)
-
11:00 本丸跡からのパノラマビューを撮影
-
12:00 地元カフェでランチ&スイーツ撮影
-
13:30 金田一温泉の足湯や路地裏の雰囲気ある通りを撮影
-
15:00 馬仙峡で絶景ショット
-
17:00 宿泊先で夕景撮影&ゆったりタイム
自然光を活かした撮影がしやすいスポットが多数あるため、旅の記録としてSNS映えも抜群。特に九戸城の堀や土塁、馬仙峡の大岩盤は絶好の撮影ポイントです。
グルメ
二戸名物「南部せんべい」の魅力
二戸市に来たら、ぜひ味わいたい郷土グルメのひとつが「南部せんべい」です。南部せんべいは、岩手県北部を中心とした南部地方に古くから伝わる素朴なお菓子で、小麦粉をベースにした生地を鉄製の型に入れて焼き上げるのが特徴です。
基本の味はごま入りが定番ですが、近年ではピーナッツ、くるみ、かぼちゃの種入り、さらにはカレー味やチーズ味などバリエーションも豊富になってきています。サクッとした食感と香ばしさがあり、お茶請けにもお酒のおつまみにも相性抜群。
また、せんべいを“割って食べる”文化も特徴的。岩手では昔から「せんべいは割って分け合うもの」とされ、家族や友人との団らんのシンボルでもあります。
二戸市内には老舗のせんべい店が複数あり、焼きたてのせんべいが購入できるお店も。特におすすめなのが「巌手屋(いわてや)」や「二戸せんべい本舗」で、試食や工場見学も楽しめます。
お土産としても人気が高く、軽くて日持ちするため旅行中の荷物にもなりません。味もさまざまで、詰め合わせも販売されているので、配る用のお土産にもぴったりです。
素朴で懐かしい味わいの中に、南部地方の歴史と人の温かさが感じられる南部せんべい。九戸城観光の合間や帰り際に、ぜひ一度その香ばしさを楽しんでみてください。
馬肉文化が根付く「桜鍋・馬刺し」
岩手県北部、特に九戸周辺では、昔から馬肉を食す文化が根付いています。かつては農作業や運搬などで使われていた馬の命を最後まで大切にいただくという考えから、馬肉が食文化として発展してきました。いまでも「桜鍋(さくらなべ)」や「馬刺し」といった料理が郷土料理として親しまれています。
「桜鍋」とは、味噌ベースのだしに馬肉や季節の野菜を入れて煮込む鍋料理。味噌のコクと馬肉のあっさりしたうま味が絶妙に絡み合い、寒い季節には心から温まる一品です。
一方「馬刺し」は、新鮮な馬肉を薄くスライスし、生姜やにんにく醤油でいただくのが定番。クセがなく、口の中でとろけるような食感が人気で、県外からの観光客にも好評です。
市内の食事処や居酒屋では、これらの馬肉料理を提供している店がいくつもあり、地元ならではの味を楽しめます。特に「大昌園」や「味処まるまつ」などは、地元の人にも愛されている名店で、旅行者にも安心しておすすめできるスポットです。
健康面でも、馬肉は高たんぱく・低脂肪で栄養価が高く、女性やアスリートからも注目されています。九戸城を訪れた際には、こうした「地元の知恵と歴史」が詰まったグルメをぜひ味わってみてください。
比内地鶏を使った絶品焼き鳥・親子丼
比内地鶏といえば秋田県の名産品として有名ですが、実は岩手県北部の飲食店でも広く取り扱われています。二戸市近郊の飲食店では、秋田から直送される比内地鶏を使った料理が人気で、焼き鳥や親子丼は観光客にとって外せないグルメの一つです。
比内地鶏は、肉質がしっかりしており、噛むたびに旨味が広がるのが特徴。特に炭火で焼かれた焼き鳥は香ばしさが際立ち、脂の甘みと濃厚な肉の風味が絶妙なバランスを生み出します。モモやムネのほか、砂肝やレバーなどの部位も提供している店が多く、食べ比べも楽しめます。
親子丼もまた絶品で、比内地鶏のコクのある旨味と、地元産の新鮮な卵がとろけるように絡み合い、一口食べた瞬間に幸せな気分になれる味わいです。ご飯は岩手県産のお米を使っており、粒立ちが良く、濃厚な鶏と卵の味をしっかりと受け止めてくれます。
おすすめの店舗としては、地元の人気店「鳥蔵(とりくら)」や「しんちゃん食堂」などがあります。どちらもリーズナブルな価格で本格的な比内地鶏料理が楽しめることで、観光客はもちろん地元の人々にも愛されています。
旅の合間に、温かいごはんと香ばしい鶏肉で心も体も満たされる——そんなひとときを提供してくれる比内地鶏料理は、九戸城観光のランチや夕食に最適です。
二戸の郷土そば「けいらんそば」と山菜料理
岩手県北部では、冷涼な気候を活かして栽培されるそばが特産品のひとつとなっています。中でも「けいらんそば」という、もちもちした団子入りのそばは、知る人ぞ知る郷土料理。素朴な味わいと食べごたえで、多くの観光客の心を掴んでいます。
「けいらん」とは「鶏卵」ではなく、「慶卵」とも書かれ、祝いごとの際に供されてきた団子を意味します。この団子にはあんこが入っていることもあり、甘じょっぱい味のハーモニーが特徴です。あたたかいそばつゆに浮かべると、だんだんと団子がとろけ出し、独特の風味と口当たりが楽しめます。
また、山の幸に恵まれた地域であることから、春から秋にかけては「山菜そば」もおすすめ。わらび、ぜんまい、ふき、こごみなど、季節ごとの旬の山菜がふんだんに使われており、滋味深い味わいが特徴です。
地元で人気のそば屋には「そば処 佐々木」や「三平庵」などがあり、どちらも手打ちそばを提供しており、香り高い一杯を味わうことができます。観光の途中に立ち寄るにもアクセスしやすい立地です。
体にやさしく、心も温まる郷土そばは、歴史ある九戸城の空気と相まって、旅の味わいをさらに深めてくれる存在です。
素朴な甘さが魅力の地元スイーツ
旅の終わりには、地元ならではのスイーツでほっとひと息つきたくなりますよね。二戸エリアには、素朴ながらも深い味わいを楽しめる和スイーツ・洋スイーツがたくさんあります。地元の素材を使い、手間暇かけて作られたお菓子は、お土産にもぴったりです。
まずおすすめなのが、「しそ巻き大福」。餅の中に甘さ控えめのあんこが入り、外側を香り高い紫蘇の葉で巻いた一品です。紫蘇のほのかな酸味がアクセントとなり、甘さとのバランスが絶妙。見た目もかわいらしく、女性に人気です。
次に紹介したいのが、地元産のブルーベリーを使った「ブルーベリージャムクッキー」や「ブルーベリーチーズタルト」。この地域ではブルーベリーの栽培が盛んで、甘みと酸味のバランスが良く、スイーツに最適。二戸駅前の洋菓子店「カフェ・ノワール」では、地元の素材を活かしたスイーツが楽しめます。
また、昔ながらの製法で作られる「黒糖まんじゅう」や「くるみゆべし」も人気。これらは観光案内所や地元スーパーでも手軽に購入できるので、帰路の新幹線内でのおやつにもおすすめです。
「観光の締めくくりは甘いもので」と考える方にとって、これらの地元スイーツは、旅の思い出をより甘くしてくれる存在です。
観光情報
アクセス情報:二戸市・九戸城への行き方
九戸城跡は、岩手県二戸市に位置しており、公共交通でもマイカーでもアクセスしやすい立地にあります。観光のスタート地点となるのは、東北新幹線「二戸駅」。ここから九戸城までのアクセス手段は以下の通りです。
【公共交通の場合】
-
東北新幹線「二戸駅」下車
-
二戸駅東口より タクシーで約10分
-
または、岩手県北バス「九戸城跡前」行きに乗車し、約15分
バスの本数は限られているため、事前に時刻表を確認しておくのがおすすめです。観光案内所でも情報提供してくれます。
【車利用の場合】
-
八戸自動車道「一戸IC」から約20分
-
東北自動車道「十和田IC」から約35分
現地には**無料駐車場(普通車20台程度)**が完備されており、マイカーでのアクセスも安心です。
また、観光案内所や周辺施設で貸自転車のサービスもあるため、駅から自転車でのんびり向かうこともできます(片道約30分程度)。道中は穏やかな田園風景が広がっており、天気の良い日はサイクリングもおすすめです。
おすすめの訪問時期と気候
九戸城跡を訪れるなら、やはり気候の安定した春と秋がベストシーズンです。季節ごとに異なる魅力があり、自然と歴史の融合を最大限に楽しむことができます。
【春(4月中旬〜5月上旬)】
-
桜の名所として知られており、満開時期には見事な花景色
-
朝のひんやりとした空気と花の香りが印象的
【夏(6月〜8月)】
-
新緑が美しく、日陰の多い城跡は涼しい散策スポット
-
虫除けと熱中症対策が必要
【秋(10月中旬〜11月上旬)】
-
木々が赤や黄色に染まり、写真映え抜群
-
観光客の数も程よく、ゆっくり見学可能
【冬(12月〜2月)】
-
雪化粧した城跡は幻想的な風景に
-
足元が滑りやすいため、滑り止め付きの靴が推奨
二戸エリアは内陸型気候で、朝晩の冷え込みが強い傾向があります。春秋でも羽織ものを持参するなど、服装には注意が必要です。
九戸城周辺の観光スポット
九戸城観光とセットで訪れたい周辺スポットも充実しています。特に歴史・自然・体験型の観光施設が多く、1日〜2日の滞在でも飽きることがありません。
🔹 馬仙峡展望台
-
巨岩「男神岩」「女神岩」を望む絶景スポット
-
城跡から車で約15分
🔹 南部美人 酒蔵見学(要予約)
-
地元が誇る銘酒「南部美人」の製造工程を見学
-
試飲体験あり、城跡から車で約10分
🔹 石切所温泉「夢の湯」
-
日帰り入浴が可能な温泉施設
-
徒歩でもアクセス可能(約20分)
🔹 二戸市シビックセンター
-
地域の文化・歴史を紹介する多目的施設
-
展示ホールでは特別企画展も開催される
観光の合間に立ち寄れるカフェや直売所も多く、地元野菜や工芸品をお土産に買うのもおすすめです。
周辺の道の駅と直売所
地元ならではの味覚や特産品を探すなら、「道の駅」や「直売所」も欠かせません。特にドライブ観光の途中に立ち寄ると、地元の魅力をぐっと身近に感じられます。
道の駅 くじ やませ土風館
-
海産物、山菜、手作りスイーツなど多彩な品ぞろえ
-
地元作家の工芸品や雑貨も人気
道の駅 にしね
-
八幡平産のりんご、ブルーベリー製品が充実
-
観光案内所や軽食コーナーも併設
JA直売所 にのへふれあいプラザ
-
朝採れ野菜や手作り味噌、漬物などが人気
-
観光客だけでなく地元の方にも愛されるお店
道の駅は、地域と観光客をつなぐ交流の場。旅の思い出に残る「食」と「人とのふれあい」を楽しめる場所です。
観光所要時間とモデル滞在プラン
九戸城跡を含む観光の所要時間は、短くて2時間〜、じっくり見学で半日〜1日が目安です。九戸城単体だけなら約1.5時間で見学可能ですが、周辺スポットを含めるとスケジュールに余裕を持たせるのがポイントです。
🔹 半日プラン
-
九戸城跡 → 資料館 → 昼食 → 道の駅 → 温泉
🔹 1日プラン
-
九戸城跡 → 城下町散策 → 昼食 → 馬仙峡 → 酒蔵見学 → お土産購入
🔹 1泊2日プラン
-
【1日目】九戸城跡 → 南部美人酒蔵 → 金田一温泉宿泊
-
【2日目】朝風呂 → 馬仙峡 → ランチ → 道の駅でお土産 → 帰宅
無理なく楽しめるルートを組むことで、九戸の自然と歴史を余すことなく満喫できます。
まとめ
九戸城は、戦国時代末期の激動を生きた九戸政実の舞台として、今も多くの歴史ファンや観光客を魅了しています。見どころは、土塁や堀、曲輪などのリアルな遺構だけでなく、豊かな自然や四季折々の風景、そして周辺に点在する魅力的な温泉宿やグルメ、体験型観光スポットの数々。
宿泊施設も多彩で、温泉を楽しめる宿から民話の世界に触れられる旅館まで揃っており、観光スタイルに合わせたプランが立てやすいのも大きな魅力です。
グルメも、南部せんべいや馬肉料理、地元そば、スイーツなどバラエティに富み、五感で楽しむ旅が実現します。アクセスの良さや観光サポート体制も整っているため、初めての訪問でも安心です。
歴史・自然・人情が調和する九戸の地で、あなたも自分だけの「旅のストーリー」を見つけてみませんか?